ワークライフバランス
働き方改革への取り組み
多様な人材が活躍できる環境をつくるために働き方・休み方改革の推進は必須と考えています。当社では2009年度より労使メンバーにて構成する「労働時間対策委員会」を設置して、労働時間・休日・休暇等について法令を上回る当社独自の社内管理基準を設けて労働時間管理の基準を示し、働く環境の改善を推進しています。



「育児と仕事の両立ガイドブック」の発行
育児と仕事の両立を支援する施策として、まずは「育児と仕事の両立ガイドブック」を作成することから始めました。
目的はふたつ。ひとつは「両立支援の対象は女性のみ」という意識の払拭、もうひとつは「制度内容を多くの人に理解してもらうこと」です。実はそれ以前も同様の冊子はありましたが、支援のあり方の見直しに伴い、大幅にリニューアルしました。
具体的には、「ママ・パパ・ボス」をキーワードとして、両立支援制度や給付金等の説明、妊娠出産から育休復帰後までの各期間における「ママ・パパ・ボス」のToDo、「小1の壁」や「短時間勤務のメリットデメリット」といったコラム、先輩ママ・パパ・ボスの体験談を掲載しています。
本ガイドブックでは、特にママ・パパの上司となっている「ボス」向けの内容を充実させることにこだわりました。同じページに、ママ・パパ向けと「ボス」向けの内容を左右に並列記載し、お互いの状況を自然と知ることができる構成にしています。
この理由は、育児と仕事の両立は「ママ・パパ」本人の努力に加えて「ボス」のマネジメントが成否を分けると考えているためです。相互理解に努めるためのツールとして社員に活用いただいており、現在では配偶者の妊娠を報告した男性社員、いわゆる「プレパパ」に、ボスから育休取得の話をされる事例も出てきています。今後も両立の成功事例を少しずつ積み上げていきます。
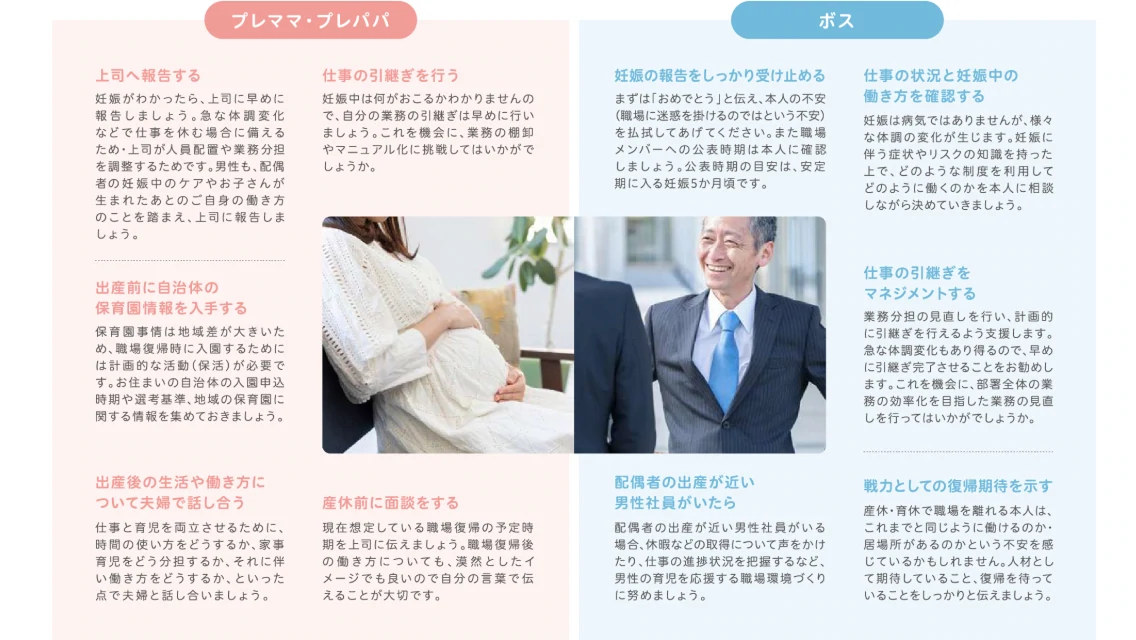
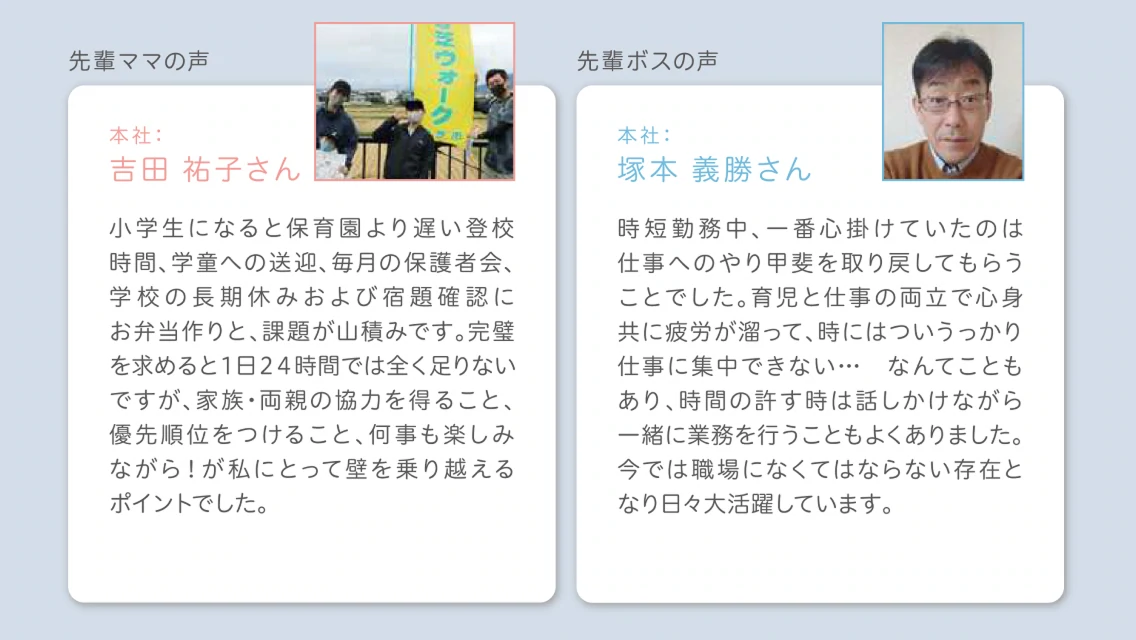
男性育児休業取得促進の取り組み

当社では、男女問わず育児と仕事を両立できることが組織力強化に繋がると考えており、男性社員の育児休業の取得を推奨しています。
例えば、社員本人または配偶者が出産した際に10日間取得できる有給の特別休暇は、多くの社員に利用されています。また、育児休業中に部分的に勤務することを認めており(労使協定に基づく一時的・臨時的な就労に限ります)、研修への参加など、仕事と育児を両立させながらスキルアップする機会も提供しています。
これらの制度により、金銭面や業務負担、キャリアに対する不安が軽減され、男性育休取得率と取得日数が大きく向上しています。こうした取り組みは、会社(人事部)主導だけでなく、労働組合からの提案によっても導入されており、労使が一丸となって「働きやすい会社」を作り上げています。
今後も社内のニーズを反映させた制度改善を進め、社員全員がよりよい職場環境で成長できるよう努めてまいります。
各種制度
従業員のワークライフバランスを重視し、多様な人材が活躍できるよう、さまざまな制度を導入しています。
働き方に関する制度
| 在宅勤務制度 | 週2日を上限として自宅で勤務することができる制度。(適用業務の定めあり) |
|---|---|
| フレックスタイム勤務制度 | 1ヵ月の総労働時間の範囲内で、毎日の始業・終業時刻を本人の決定に委ねる制度。(適用部門の定めあり) |
| ノー残業デー (定時退社日) |
毎週1日を事業所のノー残業デーと定めて、残業時間削減に取り組む制度。 |
| 連続休暇 | 年次有給休暇を連続して2日以上取得する「連続休暇」を毎年1回取得することを推奨。 |
| 積立休暇 | 有効期間が満了した年次有給休暇を最大55日間まで積み立てて傷病時などに利用できる休暇。 |
| 特別休暇 | 結婚、出産、弔事などの際に年次有給休暇とは別に取得できる休暇(有給)。 |
| 休日 | 完全週休2日制のほか、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始の年間125日。 |
| 有給休暇 | 初年度は入社時に4日、3ヵ月の見習期間後に12日付与。(最大22日付与) |
育児支援制度
| 母性健康管理 | 妊娠中の健康管理を目的とした、通院休暇(1~4週間に1日の休暇)、通勤緩和(始終業時刻の繰上げ・繰下げ、通勤手段変更)、休息の措置、作業制限措置(業務低減・転換等)の措置。 |
|---|---|
| 産前休暇 | 出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合14週間前)から請求できる休暇。 |
| 産後休暇 | 出産の翌日から8週間の休暇。 |
| 配偶者出産休暇 | 配偶者出産時の入退院の付き添い、世話、出生届の届出等のために3日間取得できる特別休暇(有給)。 |
| 出産時育児休業 (産後パパ育休) |
子の出生後8週間以内に、4週間まで取得できる育児休業。 |
| 育児休業 | 子が1歳になるまで(女性は産後休暇終了後から、男性は出産(予定)日から)取得できる休業。 |
| 育児休業時特別休暇 | 育児休業時に10日間取得できる特別休暇(有給)。 |
| 所定外・深夜労働免除 | 子が小学校就学の始期に達するまで、所定外及び深夜労働の免除を請求できる措置。 |
| 育児短時間勤務 | 子が小学校3年生を修了する年度末まで、1日の就労時間内で2時間を限度に短縮できる勤務制度。 |
| 子の看護休暇 | 子が小学校3年生を修了する年度末まで、子どもの看病、世話、通院等、年間15日、時間・半日単位で取得できる休暇。 |
介護支援制度
| 介護休業 | 要介護状態にある家族を介護するために最長2年間取得できる休業。 |
|---|---|
| 介護休暇 | 要介護状態にある家族の介護・世話のために年間15日、時間・半日単位で取得できる休暇。 |
| 介護短時間勤務 | 要介護状態にある家族を介護するために、利用開始から5年間で5回までの範囲内で、1日の就労時間内で2時間を限度に短縮できる勤務制度。 |